
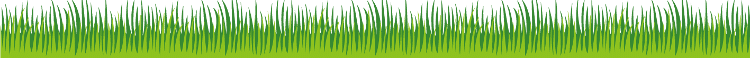
オオマドボタル (Pyrocoelia discicollis)
【種類】 ホタル科 マドボタル亜科
【分布地域】 本州・四国・九州
【活動時期】 6~7月
【エサ】 水分のみ
【大きさ】 11ミリぐらい
昼間に活動する光らないホタルの『オオマドボタル』
四角い赤い模様の上に窓のような模様があるのがチャームポイントです。
真上から見た時に、窓の部分が目で赤い部分がクチバシのペンギンの顔のようにも見えるかもしません。
数はそれほど少なくないんですけど、生息域が狭いですし活動時期が短いので簡単に出会える昆虫かと言うとなかなかそうでもないホタルです。
だからがゆえに、面白味があるホタルでもあります。
オオマドボタルに毒や害はないのか

毒はないです。
噛みつくような牙や、刺したりするようなものもないです。
変な汁を出すこともないので、危険性のない昆虫です。
いたって無害なので安心してください。
オオマドボタルは光らない昼間のホタル

光るので有名なゲンジボタルやヘイケボタルとは違って、オオマドボタルは光らないのであまりメジャーではないです。
でも、立派なホタルに間違いないですけどね。
昼間に活動しているので明るい時間に出会うことができるので、手乗りにしてまじまじ観察できるのは嬉しい限りです。
昼に出会えるからか見つけても意外とホタルと認識ないこともあります。
オオマドボタルの情報

オオマドボタルの分布
分布は、本州から四国までとなっているのですが、ひと昔前までは近畿より以西と言われていたのが徐々に分布を広げています。
一方、福岡県では絶滅危惧Ⅱ類になっている貴重な昆虫ともなっています。
オオマドボタルの特徴
オオマドボタルは、クロマドボタルに似ていて交配しているほど近い種類なのですが見た目は全然違います。
オオマドボタルは、クロマドボタルにはない胸部の赤い四角い模様があります。
この模様の入り方は、よく見かけるホタルの中でも似たパターンがないのですぐに分かるポイントですね。

でも一番の特徴は、名前の由来になっているマドですね。

上から見るとまるで目があるかのように見えてしまう窓(マド)が、ちょうど目(複眼)のすぐ下辺りに左右対称に入っています。
この窓はただの飾りではなくて、頭を引っ込めた状態の時にここから周りの状況をうかがえるになっている優れものなんです。
他にも、触覚がオバボタルと同じように11節に分かれている太くて長い鋸歯状(きょしじょう)をしています。
光らないので、フェロモンをキャッチしてメスを探すので触覚が発達しているんですね。
体は全体的にツヤのない黒で、繊細で柔らかい感じなので手で捕まえるとすぐに潰れてしまうので注意が必要なほどフワフワした感じです。
オオマドボタルの住処

川で育つのではないので、林は森、竹林などの近くにいます。
市街地ではなかなか見れないで、自然公園のような場所か木々が多い場所を目ざした方が生息していることが多いです。
オオマドボタルの生態

幼虫は陸生なので、枯れ葉や腐った木の下などに隠れながら生活しています。
意外と積極的で行動的でもあるので、葉っぱの上を移動しながら貝類や小さな昆虫を探し回ったりしています。
幼虫の時期は、ヘイケボタルやゲンジボタルのように光るのですが、成虫になると光らなくなってしまいます。
なので、全く光らないホタルではないんですよね。
成虫になったオオマドボタルは、水分補給ぐらいしかしません。
寿命は1週間程度なので、それほど長くなく尽きてしまいます。
その間に、メスを探して交尾をするのですが、メスは翅がなく白っぽい幼虫のような形をしています。全く同じホタルとは思えないほどです。
なので、成虫のオオマドボタルを飼育するのは難しいので、虫かごで少しのあいだ観察するぐらいしかできません。
冬は幼虫の状態で、枯れ葉の下や土に少し潜って寒い時期を越します。
南限の鹿児島辺りだと、冬の気温が高い日は動き出すこともあるようですが、基本的にはじっとしたままで春がくるのを待つスタイルとなっています。
一生を陸で過ごすホタルですけど、幼虫の間だけは光るので探してみると楽しいと思います。
観察のしがいのあるホタルなので、もし出会ったらじっくりと見てみてください♪



