
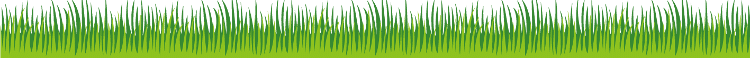
チュウレンジハバチはどんなハチ?
【種類】 ミフシハバチ科 ミフシハバチ亜科
【分布地域】 北海道・本州・四国・九州
【活動時期】 4~9月
【エサ】 花の蜜
【大きさ】 15~18ミリぐらい
黒い翅にオレンジのお腹の蜂がバラの茎にいたらそれが『チュウレンジハバチ』です。
ハチといってもスズメバチやアシナガバチのような感じではなくて、ずんぐりした見た目はあきらかに強そうな気配のないハチです。
幼虫がバラの葉を食べてしまうので、幼虫の方が有名かもしれないですね。

チュウレンジハバチには毒や害はあるのか

名前に蜂(ハチ)がはいっていますけど、毒針のある蜂とは違って毒はありません。
針すらもっていないので、危険性のないハチです。
チュレンジハバチの成虫は直接的な害はないのですが、バラ科の植物に卵を産み付けるので食害のもとになります。
茎に産卵するのですが、茎を傷つけてしまいます。
チュウレンジハバチの情報

チュウレンジハバチの分布
北海道から九州までの広い範囲に生息しています。
チュウレンジハバチの特徴
横から見ると顔以外はオレンジ色をしています。
でも、顔(頭部)、背中(胸部)、脚、翅は黒いので、上から見ると黒い虫にしか見えません。
そこまで大きくないですが、バラの茎に来ている時はすぐに目に付くと思います。
俊敏に動くタイプではなく、止まっている時はじっとしていることが多いです。
チュウレンジハバチをよく見る場所
バラには卵を産みに来るだけで、普段はバラにはいないです。
スズメバチやアシナガバチのように巣を作ることはないので、他の植物の葉の裏や上などで休んでいたりします。
チュウレンジハバチの生態

チュウレンジハバチは春から秋にかけて活動しているので、産卵から成虫までを繰り返す回数もそれに応じて多くなります。
夏の終わりに生まれた幼虫たちは土に潜って蛹(サナギ)の状態で冬を越します。
そして、春の暖かい季節になったら土の中から羽化して出てくるのをスタートし、交尾を終えたメスがバラの茎に卵を産みに行きます。
産卵は、バラの茎に産卵管というものを刺して卵を産み付けるので、硬すぎると茎に産卵管が刺さらないのでまだ柔らかい茎を狙って産卵します。
その方が、幼虫たちも孵化した時に柔らかい新葉にたどり着きやすいのもあると思います。
産卵する時は、下を向くように逆さまになって産卵するのですが、30~40個ほどの卵を産み付けています。
卵は1週間ほどで孵化します。
孵化する際に茎が縦に裂けるので茎が大きく傷ついてしまうので、場合によってはバラの成長にも影響が出てしまう。
対処法については、幼虫の方の記事に載せてありますので参考にしてみてください。





