
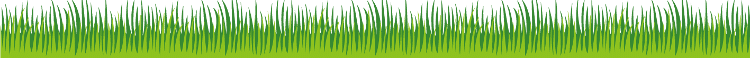
キハラゴマダラヒトリ (Spilosoma lubricipedum)
【種類】 ヒトリガ科 ヒトリガ亜科
【分布地域】 北海道・本州・四国・九州
【活動時期】 4~9月
【エサ】 食べない
【大きさ】 32~42ミリぐらい
キレイな白い翅に頭回りが白いファーのようになっていて、規則正しく黒いドット模様が素敵なオシャレさんな『キハラゴマダラヒトリ』。
黒いゴマ粒模様とも言えますかね。
パッと見で似ている蛾に、アカハラゴマダラヒトリや、幼虫の時に桜の木に大量について丸坊主にしていまうで有名な外来種のアメリカシロヒトリとはそっくりもそっくりです。
お腹の色を見ないと、似すぎて全く同じにしか見えないほど!!
でも、それぞれちゃんと生態に違いがあるので、じっくりと観察して見分けたいですね。
キハラゴマダラヒトリは毒や害はあるのか

毒はないので安心してください。
ただのかわいい蛾です。
幼虫の時も、毛むくじゃらで危ないように見ますが毒はないです。
鱗粉アレルギーの場合は、体が反応する可能性があるので注意してくださいね。
あと、黄色の汁をお尻から出すので人によっては少しかぶれる可能性があります。
害になる事もないです。
でも、幼虫の時は、桜やクワの葉や、大豆(ダイズ)などの野菜の葉を食べるので、ガーデニングや畑をしている人にとっては食害されていますので害虫です。
キハラゴマダラヒトリは顔が面白い

キハラゴマダラヒトリは正面から見ると凄くユーモアな顔をしているんです。
キハラゴマダラヒトリは手に乗せやすいので、手乗りにして写真を撮ってそのナイスなお顔をご披露しようと思ったんですが…
自分の撮った写真は、ちょっとヒゲの生えたおじさんみたいになっちゃいましたね…
もっとカワイイ感じを伝えたかったんですけど残念!!
でも、なかなかユーモアな顔なのは伝わりましたかね。
しかし、ドット模様に白いファーでオシャレさんとして紹介したのに、顔はおじさんみたいだとちょっと変な感じですね(汗)
キハラゴマダラヒトリの情報

キハラゴマダラヒトリの分布
分布は、北海道から九州までなので、沖縄以外になっています。
屋久島までは分布されています。
キハラゴマダラヒトリの特徴

キハラゴマダラヒトリの最大の特徴は、名前の通りの黄腹(キハラ)ですね。
あと、前脚の付け根辺りも同じように黄色くなっています。
この特徴が、そっくりさんのアカハラゴマダラヒトリやアメリカシロヒトリとの決定的な違いです。
稀に、アカハラゴマダラヒトリのように赤くなっていることもあるようですが、珍しいパターンなので基本的にはお腹(腹部)と前脚の付け根辺りが黄色ければキハラゴマダラヒトリになります。

翅の黒いドット模様は、個体差があるのですが左右対称になっています。
そして、何かしらのパターン模様で規則正しく並んでいます。
翅の色は、真っ白ではなくてちょっとだけ黄色がかったクリーム色に近い色をしています。
キハラゴマダラヒトリの生態

キハラゴマダラヒトリは、春の成虫になる春型と、夏に成虫になる夏型があるタイプです。
春型と夏型では、若干サイズや模様の入り方が変わってきます。
春型は、越冬した幼虫がでてくきたものです。
なんと、越冬は卵や蛹ではなくて幼体で頑張るタイプなのです!!
また、成虫になると口(口吻)がないので、エサを食べることはないです。
幼虫の時に蓄えた栄養だけで、繁殖のための体力をもたせるのは凄いことですよね。
この都合上、長く生きることができないので、カワイイ蛾ですけど飼育はちょっとかわいそうだと思います…

面白いのが、危険を感じると死んだふりをすることです。
その瞬間に、手乗りにすることが簡単にできます。
せかせかと逃げてしまわないおっとりした所が、なんともカワイイところなんですよねぇ。

なんとも優しい色合いで、つるっとした木の表面の見える『ウスキシャチホコ』 顔回りと前脚の白い毛がフサフサしているのがカッコイイ。ちょっと気品のある風格の蛾です。

名前の通り、大きな白い筋模様が入っていて茶色のカラーなので、個人的にはチョコレートとバニラのお菓子に見えてしまう『シロスジツトガ』


ベースの色が擬態色だけど、キレイに細いピンクのラインがワンポイントになっている蛾。
